【会津嶺 2024年8月号】 星々と神社
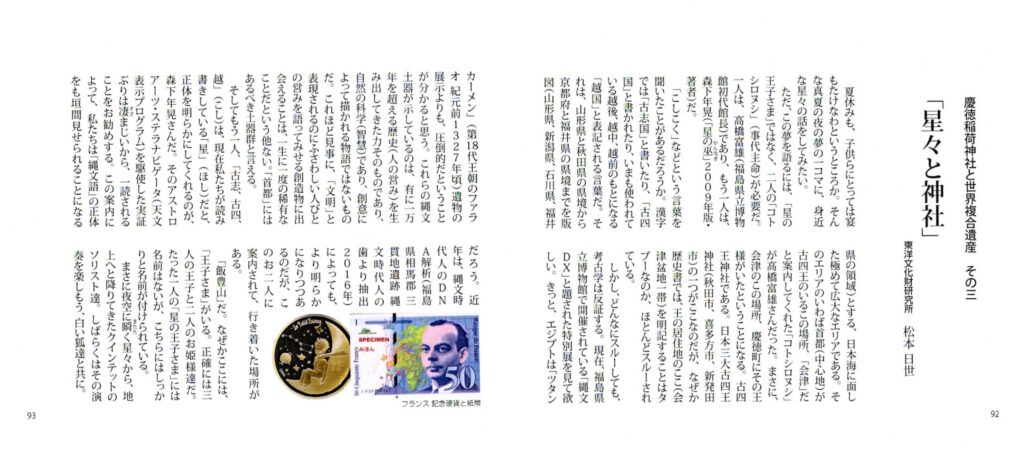
慶徳稲荷神社と世界複合遺産 その3
夏休みも、子供らにとっては宴もたけなわというところか。そん真夏の夜の夢の一コマに、身近な星々の話をしてみたい。
ただ、この夢を語るには、「星の王子さま」ではなく、二人の「コトシロヌシ」(事代主命)が必要だ。一人は、高橋富雄(福島県立博物館初代館長)であり、もう一人は、森下年晃(「星の巫(かんなぎ)」2009年版・著者)だ。
「こしこく」などという言葉を聞いたことがあるだろうか。 漢字では「古志国」と書いたり、「古四国」と書かれたり、いまも使われている越後、越中、越前のもとになる「越国」と表記される言葉だ。 それは、山形県と秋田県の県境から京都府と福井県の県境までを版図(山形県、新潟県、石川県、福井県の領域)とする、日本海に面し極めて広大なエリアである。 そのエリアのいわば首都(中心地)が古四王のいるこの場所、「会津」だと案内してくれた「コトシロヌシ」が高橋富雄さんだった。まさに、会津のこの場所、慶徳町にその王様がいたということになる。 古四王神社である。日本三大古四王神社(秋田市、喜多方市、新発田市)の一つがここなのだが、なぜか歴史書では、王の居住地のここ(会津盆地一帯)を明記することはタブーなのか、ほとんどスルーされている。
しかし、どんなにスルーしても、考古学は反証する。 現在、福島県立博物館で開催されている「縄文DX」と題された特別展を見て欲
しい。きっと、エジプトは「ツタンカーメン」(第18代王朝のファラオ 紀元前1327年頃)遺物の展示よりも、圧倒的だということが分かると思う。 これらの縄文土器が示しているのは、有に一万年を超える歴史(人の営み)を生み出してきた力そのものであり、自然の科学(智慧)であり、創意によって描かれる物語ではないものだ。これほど見事に、「文明」と表現されるのにふさわしい人びとの営みを語ってみせる創造物に出会えることは、一生に一度の稀有なことだという他ない。「首都」にはあるべき土器群と言える。
そしてもう一人、「古志、 古四、越」 (こし)は、現在私たちが読み書きしている「星」 (ほし)だと、正体を明らかにしてくれるのが、森下年晃さんだ。 そのアストロアーツ・ステラナビゲータ(天文表示プログラム)を駆使した実証ぶりは凄まじいから、一読されることをお勧めする。この案内によって、私たちは「縄文語」の正体をも垣間見せられることになるだろう。近年は、縄文時代人のDNA解析 (福島県相馬郡三貫地遺跡 縄文時代人の歯より抽出2016年)によっても、より明らかになりつつあるのだが、 このお二人に案内されて、行き着いた場所がある。
「飯豊山」だ。なぜかここには、「王子さま」がいる。正確には三人の王子と二人のお姫様達だ。たった一人の「星の王子さま」には名前はないが、こちらにはしっかりと名前が付けられている。
まさに夜空に瞬く星々から、地上へと降りてきたクインテットのソリスト達。しばらくはその演奏を楽しもう、白い狐達と共に。
東洋文化財研究所 松本 日世
