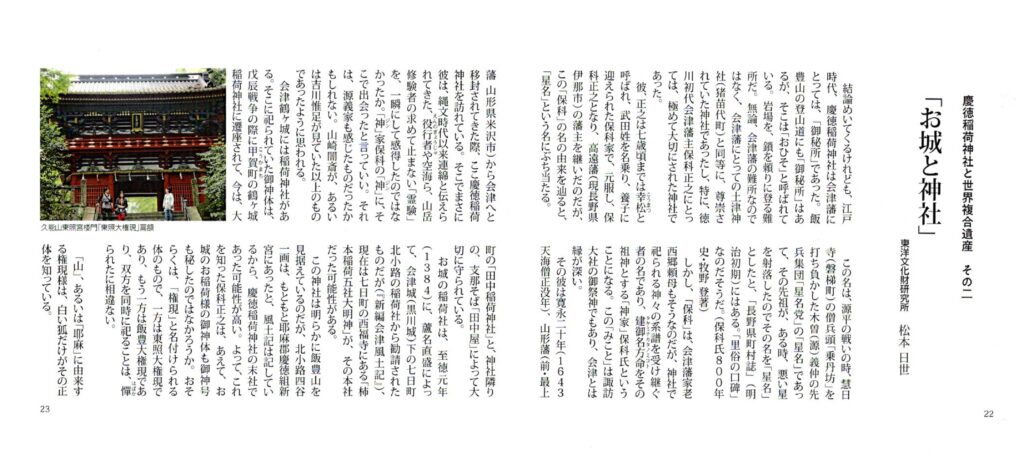【会津嶺 2024年7月号】お城と神社
慶徳稲荷神社と世界複合遺産 その2
結論めいてくるけれども、江戸時代、慶徳稲荷神社は会津藩にとっては、「御秘所」であった。 飯豊山の登山道にも「御秘所」はあるが、そこは「おひそ」と呼ばれている。岩場を、鎖を頼りに登る難所だ。無論、会津藩の難所なのではなく、会津藩にとっての土津神社(猪苗代町)と同等に、尊崇されていた神社であったし、特に、徳川初代会津藩主保科正之にとっては、極めて大切にされた神社であった。
彼、正之は七歳頃までは幸松と呼ばれ、武田姓を名乗り、養子に迎えられた保科家で、元服し、保科正之となり、高遠藩(現長野県伊那市)の藩主を継いだのだが、この「保科」の名の由来を辿ると、「星名」という名にぶち当たる。
この名は、源平の戦いの時、慧日寺(磐梯町)の僧兵頭「乗丹坊」を打ち負かした木曽(源)義仲の先兵集団「星名党」の「星名」であって、その先祖が、ある時、悪い星を射落したのでその名を「星名」としたと、「長野県町村誌」(明治初期)にはある。「里俗の口碑」なのだそうだ。(保科氏800年史・牧野 登著)
しかし、「保科」は、会津藩家老西郷頼母もそうなのだが、神社で祀られる神々の系譜を受け継ぐ者の名であり、建御名方命(タケミナカタノミコト)をその祖神とする「神家」保科氏ということになる。この「みこと」は諏訪大社の御祭神でもあり、会津とは縁が深い。
その彼は寛永二十年(1643天海僧正没年)、山形藩(前・最上藩 山形県米沢市)から会津へと移封されてきた際、ここ慶徳稲荷神社を訪れている。 そこでまさに彼は、縄文時代以来連綿と伝えられてきた、役行者や空海ら、山岳
修験者の求めて止まない「霊験」一瞬にして感得したのではなかったか。「神」家保科の「神」に、そこで出会ったと言っていい。 それは、源義家も感じたものだったかもしれない。山崎闇斎が、 あるいは吉川惟足が見ていた以上のものであったように思われる。
会津鶴ヶ城には稲荷神社がある。そこに祀られていた御神体は、戊辰戦争の際に甲賀町(こうかまち)の鶴ヶ城稲荷神社に遷座されて、今は、大町の「田中稲荷神社」と、神社隣りの、支那そば「田中屋」によって大切に守られている。
お城の稲荷社は、至徳元年(1384)に、蘆名直盛によって、会津城(黒川城)下の七日町北小路の稲荷社から勧請されたものだが(『新編会津風土記』)、
現在は七日町の西福寺にある「柿本稲荷五社大明神」が、 その本社だった可能性がある。
この神社は明らかに飯豊山を見据えているのだが、北小路四谷一画は、もともと耶麻郡慶徳組新宮にあったと、風土記は記しているから、慶徳稲荷神社の末社であった可能性が高い。よって、これを知った保科正之は、あえて、お城のお稲荷様の御神体も御神号も秘したのではなかろうか。おそらくは、「権現」と名付けられる体のもので、一方は東照大権現であり、もう一方は飯豊大権現であり、双方を同時に祀ることは、憚(はばか)られたに相違ない。
「山」、あるいは「耶麻」に由来する権現様は、白い狐だけがその正体を知っている。
東洋文化財研究所 松本 日世